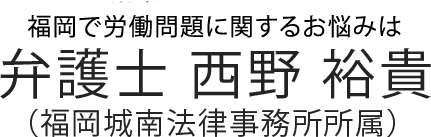【残業代・労働組合】トラックドライバーの労働組合加入後にされた配車差別が不当労働行為に該当し配車差別前の平均賃金との差額の損害賠償請求を認めた東輪ケミカル事件・福岡地小倉支判令和7年2月6日労働判例ジャーナル161号を解説します。
【音声解説】https://drive.google.com/file/d/1sbxNcrtlrRoTe8cwt4ZE3yrC-0Ggdf3j/view?usp=drive_link
1 本件のポイント
本件はトラックドライバーが①労働組合加入後にされた配車差別が不当労働行為に該当し配車差別前の平均賃金との差額の損害賠償と、②残業代請求をした事案です。②については、重要な論点として、(ア)乗務手当が残業代が多くなる月給制(労基則19条1項1号)に該当するのか、残業代が少なくなる出来高払制(労基則19条1項6号)に該当するのか、(イ)消防法上の危険物に該当する化学薬品を積載するなどして長時間停車していた時間が労働時間に該当するのかが争われた事件です。
論点が多いため、この記事では①の配車差別のみを取り扱います。
なお、出来高払制に該当した場合、残業代が少なくなってしまうことについては、【残業代】歩合制(出来高払制その他の請負制)は低い残業代・働かせ放題になりやすく注意が必要です。の記事やhttps://drive.google.com/file/d/15Hj_wv-RKJLFe9GvvM3ShJaNOZZSnAOr/view?usp=drivesdkの動画をご覧ください。
2 出来事
令和3年12月17日、原告全国一般(北九州支部を含む)は被告に就業規則等の開示と未払賃金の支払を求め、団体交渉を申入れました。翌18日、原告運転手3名は各自名義で未払賃金の支払催告書を送付。被告は24日、団交日程を令和4年1月14日と決定しました。他方で、被告の親会社H社の社長・人事部長Jらは要求・催告を受け、原告運転手らに対し同年1月から長距離・休日出勤を外す本件配車措置を実施することを決定し、12月末までに現場責任者Gへ指示、Gは1月5日に翌6日からの実施を告知しました。1月14日の団交で原告らは配車措置の停止を求めましたが被告はこれを拒否しました。被告では固定給が低く、長距離・休日手当等が賃金の2~3割を占め、配車措置後は原告らの手当が減少しました。
3 被告の主張
時間外労働の量は従業員ごとに異なるのが通常であり、原告らに割増賃金が生じないのは実労働がないためで経済的不利益とはいえない、本件配車措置は高額な未払賃金請求への対応として一時的に実施し、長距離乗務の緊張負荷等、安全管理上の懸念にも配慮した措置であって、反労組的意思はないなどと主張しました。
4 裁判所の判断
⑴ 判断枠組み
「一般的に、会社には従業員に残業を命ずる義務があるわけではないが、残業手当が従業員の賃金に対して相当の比率を占めているという労働事情のもとにおいては、長期間継続して残業を命じられないことは従業員にとって経済的に大きな打撃となるものであるから、いずれの従業員に対しても残業を命ずることができる場合において、特定の労働組合の組合員に対して一切残業を命じないという取扱上の差異を設けるについては、そうすることに合理的な理由が肯定されない限り、その取扱いは当該労働組合の組合員であるがゆえの差別的「不利益取扱い」であるといわなければならず、同時に、それは、同組合員を経済的に圧迫することにより組合内部の動揺や組合員の脱退等による組織の弱体化を図るものとして、その所属組合に対する「支配介入」を構成するものというべきである(最高裁判所昭和53年(行ツ)第40号同60年4月23日第三小法廷判決・民集39巻3号730頁参照)。」としました。
⑵ この事案で不利益取扱い・支配介入にあたるか
裁判所は、まず、被告の賃金体系では長距離・休日出勤手当が総支給の2~3割を占め、原告らには従前どおり長距離・休日配車を受けられる合理的期待があったと認定しました。
続けて、被告において業務量減少などの事情はなく、原告組合員は本件配車措置の停止を求めていたことなどからすると原告組合員のみを時間外労働から外す合理的理由は見当たらないとしました。
被告主張に対しては、組合員である原告運転手らの未払賃金の請求に対し、何らの交渉をすることもなく本件配車措置を講じることは、労働組合の正当な活動を妨げる目的があると推認するほかないこと、休日出勤にいかなる安全管理上の問題があると判断したのか不明であること、被告の完全親会社である株式会社Hで管理本部の人事部長を務めるJが本件訴訟提起後の令和5年6月7日に実施された別件救済申立事件の審問において、本件配車措置を執った理由について、とにかく請求額を増やしたくない、それ以上の答えはないなどと述べていたこと、完全管理上の問題があるのであれば運転手に休息の実態などを聴き取って本件配車措置以外の代替措置が検討されて然るべきであるが被告が代替措置を検討したとは認められないことなどを指摘して不利益取扱い・支配介入に該当すると認めました。
⑶ 損害額
配車差別前の平均賃金と実際に支給された金額の差額の損害賠償請求を認めました。
4 労働組合の重要性
本件では、労働組合法7条の不利益取扱い(1号)、支配介入(3号)に該当すると判断され、損害賠償請求が認められました。もし、労働組合に加入しなかったら、会社の問題点を指摘するなどして配車差別を受けたとしても、労働組合法に違反するという主張ができず、少なくとも、本件の原告が主張したような損害賠償請求は認められませんでした。
労働者が労働環境を改善するために会社に対して一定の発言(それは会社にとっては耳が痛い発言)をしたときに、労働者を不利益に取り扱うことが考えられます。
労働者としては自身の身を守るために労働組合に加入しておくということが重要でしょう。