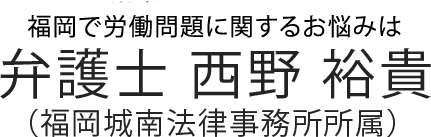【労災・過労死】トラックドライバーが急性心筋梗塞により死亡し、その原因が長時間労働等にあるとして労災申請したもの、停車時間が労働時間に該当しないことなどから不支給処分の取消しが認められなかった国・春日部労基署長事件・東京地判令和6年11月11日労働経済判例速報2581号10頁を解説します。
【音声解説】https://drive.google.com/file/d/1rm0L5Qpq93Yzl2z0HpwFF4_po_3q39kq/view?usp=sharing
1 本件のポイント
本判決が与えてくれる教訓は、労災申請するには「労働時間の管理に用いられるタイムカードやICカードの労働時間を鵜呑みにするのではなく『労働実態』を見よ」ということだと思います。
原告(亡くなったトラックドライバーの妻)は、労働時間(始業時刻と終業時刻)の管理に用いられていたICカードの時刻を前提に脳心臓疾患の労災認定基準(【労災】脳・心臓疾患の労災認定基準の基本を説明します。)を超える時間外労働時間があると主張したようです。
しかし、裁判所は、始業時刻と終業時刻との間には、比較的長時間の労働時間に当たらない停車時間があると認め、その結果、脳心臓疾患の労災認定基準で求められる時間外労働(発症前1カ月100時間、発症前2ないし6か月の平均80時間)がなく、その他の事情を考慮しても労災(業務上の疾病)に該当しないと判断しました。
労働時間の管理に用いられるタイムカードやICカードがある場合には、確かに、その時間を元にして脳心臓疾患の労災認定基準を超える時間外労働時間があれば労災申請をしたくなります。
もっとも、労災申請(特に、死亡事案)には多くの労力、時間、お金がかかります。労災申請が認められるかの見通しをしっかり検討することは、遺族のその後の人生との関係でとても重要だと思います。
労働実態(特に、停車時間など労働時間に当たるか疑義が出そうな時間があればその時間の労働実態)をしっかり確認したいうえで、タイムカードやICカードによる労働時間が認定されるのかをしっかり検討する必要があると思います。
2 原告の主張
原告は、ICカードの時間をもとに、労働時間を算定したようであり、発症前180日間の時間外労働時間は(計算方法によって若干前後するものの)1カ月平均78間39分~85時間19分である(つまり、認定基準に相当する、または、超える時間外労働時間がある)と主張しました。
3 被告の主張
被告は、原告の夫(以下「被災労働者」といいます。)は始業時刻から終業時刻までの間に、停車時間が多くあり、その時間は休憩時間であると主張しました。
4 裁判所の判断
以下「」部分は、関連する部分を原文のまま抜粋しています
⑴ 被災労働者の業務内容
「 (1)被災労働者を含む八潮営業所のトラック運転手の1日の業務について
原告を含む八潮営業所のトラック運転手は、八潮営業所に出勤した後、ICカードに打刻し、アルコールチェックや点呼を行い、トラックに乗車して草加営業所に向かい、草加営業所到着後、当日配送予定の荷物を選別してフォークリフトでトラックに積み込み、納品先に向けてトラックを運転し、納品先に到着すると、荷台で卸す荷物を指示し、配送先の従業員が荷下ろしを行っていた。なお、納品先への納品時間・到着時刻の指定もなかった。運転手は、配送が終了すると、八潮営業所に帰所し、アルコールチェック、ICカードに打刻し、点呼を行い、退勤した。(乙2、10、11)」
⑵ 会社における停車時間の扱い
「(4)被告が主張する停車時間(争点項目B~D)について
被災労働者の令和元年11月5日から令和2年5月2日までの出勤時刻及び退出時刻は、ICカードによって打刻された当該時刻であり、被災労働者の出勤簿上では、被告が主張する停車時間がいずれも休憩時間とされておらず(甲18、乙7)、また、本件会社は、被災労働者の使用していたトラックのタコグラフを管理していた(乙2)。
草加営業所又は辰巳第一での停車時間の実態は、被災労働者が、最後の配送先で納品作業を終えた後、配送先から草加営業所又は辰巳第一まで車両を移動させ、八潮営業所に帰所するまでの間に車両を停車させていた時間であった(争いがない)。
H又はI付近での停車時間は、被災労働者が、当該就業日の最終配送先であるH又はIで納品作業を終えた後、配送先から車両を移動させ、八潮営業所に帰所するまでの間に車両を停車させていた時間であった。(乙29)」
「(5)本件会社の被災労働者に対する時間外手当の支払について
本件会社は、賃金規程において、基本給等のほか、車両運行による運賃収入・距離・作業等に基づいて算定される業績時間外手当を定めており、令和元年10月以降、被災労働者に対し、当該手当を支払う一方、時間外労働時間に応じた割増賃金を支払っていなかった(甲36、46、乙2)。」
「 3 被災労働者の実労働時間について
(1)上記2の認定事実を踏まえると、被告が主張する停車時間は、いずれも被災労働者が全ての配送を終えた後の停車であって(認定事実(4))、本件会社は、これらの停車時間を把握していたものの、これに対する時間外手当を支払っていなかったこと(認定事実(5))からすれば、本件会社においてもこれらの停車時間を労働時間として取り扱っていなかったものといえる。
また、これらの停車時間は、いずれも全ての配送を終えた後、直ちに八潮営業所に帰所するのではなく、車両をいったん各停車場所まで移動させた上、数時間の停車を続けていたものであったことからすると、当該停車時間中に被災労働者が行うべき具体的な業務が存在していたと認めることはできない。」
⑶ 原告の主張に対する判示部分
「(2)これに対し、原告は、草加営業所での停車時間については、被災労働者が車両の洗車や他の運転手の荷積みに協力していたと主張する。
しかし、草加営業所は、J株式会社が所有する物流センターであり、本件会社が管理する場所ではなく、また、洗車設備もなかったというのであるから(乙23、26)、本件会社の従業員である被災労働者が同所において大型貨物自動車の洗車を行っていたとは通常考え難く、原告も、被災労働者が草加営業所において洗車等を行っていた状況を直接視認したわけでもない(甲45、原告本人)。
また、本件会社のトラック運転手が草加営業所において他の運転手の荷積みを手伝うことは通常の業務に含まれておらず(認定事実(1))、配送順によって荷積みをする順番を決める必要があることも考慮すると、運転手本人が自身の責任において行うものであったといえ、他の運転手の荷積みをすることも考え難い(乙27)。
そして、被災労働者の同僚が被災労働者の仮眠する姿を目撃したことがあること(乙10、11)や、被災労働者の使用していたトラックに布団が積み込まれていたこと(乙23)、草加営業所の敷地が広く長時間駐車して休憩することに適した場所であること(甲47、乙22)からすれば、草加営業所での停車時間中に、被災労働者が仮眠していた可能性も否定することができない。」
⑷ 時間外労働時間の認定
「被災労働者の発症前6か月間の時間外労働時間数は、発症前1か月間において100時間を超えず、また、発症前2ないし6か月間にわたる1か月間当たりの時間外労働時間数についてみても、それぞれ50時間40分、61時間02分、61時間40分、64時間18分、68時間03分にとどまるから、認定基準の定めを充足するとはいえず、被災労働者が長期間の過重業務をしていたと認めることはできない。」
⑸ 時間外労働時間のほかの考慮要素について
「被災労働者の従事した貨物運送業務は貨物積載量によって負担が増加することがあり(甲31、34)、深夜に業務を行うこともあったこと(認定事実(2))からすれば、被災労働者がトラック運転業務により一定の負荷を負っていたことは否定し難いが、発症前6か月以前の時間外労働時間は、認定基準においてあくまで付加的要因という位置づけにとどまり、被災労働者が1週間に1度は公休日があり、休養をとることができたこと(認定事実(2))、終業から翌始業までの勤務間インターバルが短い日があるものの連続的かつ恒常的に短い状況にはなかったこと(乙17)、被災労働者の従事していた業務内容(認定事実(1)及び(3))に照らしても運送業務に伴う交通法規遵守及び安全運転の履行を超えた生命・財産の重大な危険にさらされていたとまではいえないことからすれば、これらの原告の主張を踏まえても、本件疾病の発症に業務起因性があると認めることはできない。」